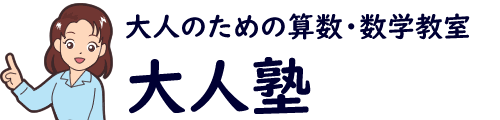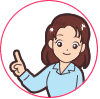
このページは、2011年より適性検査対策講座を提供している大人塾が、 SPI3-Hの試験内容と効果的な学習方法をまとめたものです。
SPI-Hとは
SPI3-Hは、リクルート社が提供するペーパーテスト形式の適性検査です。
HはHigh school(高校)を意味し、もともとは高校生の基礎学力を測定する目的で作られました。
どのような人が受ける検査?
現在は、公務員試験の中途採用などで利用されることが増えています。 大卒採用向けのSPI-Uや中途採用向けのSPI-Gと比較すると、難易度は易しく設定されています。
試験の基本情報
SPI-Hの特徴
Point
01
計算問題が全体の約3分の1を占める
40問中12問は計算問題(整数・分数・小数の四則演算)です。 文章問題ではないため、計算練習を重ねて確実に12問すべてを正解することで、残りの28問に余裕を持って取り組むことができます。
Point
02
小学生レベルの文章問題
SPI-Hの文章問題は、小学生レベルの内容です。
年齢算、濃度算、速度算など、基本的な文章問題が中心に出題されます。
Point
03
推論問題の条件が多い
SPI-Hの推論問題は、SPI-UやSPI-Gと比較すると条件が多く複雑に見えます。 しかし、実は条件が多いからこそ答えにたどり着きやすい特徴があります。
出題範囲
基本計算
整数・小数・分数の四則演算
文章問題・応用問題
集合、年齢算、割合、濃度算、比、損益算、仕事算、速度算、
数学・論理分野
場合の数、確率、図表の読取、グラフの領域、推論
効果的な学習の進め方
SPI-Hは難易度が易しいため、基礎を確実に固めることが合格への近道です。
- 計算があやふや → 基礎計算から
- 方程式の立て方が分からない → 方程式の基本から
- 割合が理解できない → 割合を重点的に
基礎の基礎から、無理なく積み上げていく。一見遠回りですが、これが確実に力をつける方法です。
SPI3-H対策の勉強方法
1. 計算力の強化
40問中12問は計算問題です。文章問題ではないため、計算練習を重ねて確実に12問すべてを正解することで、残りの28問に余裕を持って取り組むことができます。
計算が苦手な方は、大人塾で用意している「基礎計算コース(無料)」をご利用ください。 https://keisan.otona-juku.com/
試験本番まで、1日わずか5分でも継続して計算練習の時間を確保しましょう。
2. 方程式の習得
文章問題を解くためには方程式の知識が必要です。 特に一次方程式は確実にマスターしましょう。
方程式ができると、文章問題で何を求められているかが明確になり、解答の道筋が見えやすくなります。
3. 割合の完全理解
割合は以下の分野で必要となる基礎概念です。
- 集合
- 濃度算
- 比
- 損益算
- 図表の読取
- 推論
割合をマスターすることで、これらの問題を確実に得点できるようになります。 簡単な割合の文章問題から始めて、何を求められているかを把握する練習を積みましょう。
4. 推論問題への取り組み
SPI-Hの推論問題は、条件が多く複雑に見えますが、実は条件が多いからこそ答えにたどり着きやすい特徴があります。
焦らず、一つひとつの条件を丁寧に整理する練習を重ねることが重要です。 頭の中だけで考えず、必ず紙に書き出して整理しましょう。
日常学習のポイント
計算練習を継続する
計算問題は練習量に比例して速度と正確性が向上します。 また、計算力が向上すると文章題を読む余裕も生まれます。
計算が苦手な人は、文章題の数字ばかりに注目してしまい、その数字が何を表しているかを理解できない傾向があります。
短時間でも毎日続ける
試験本番まで、1日わずか5分でも継続して計算練習の時間を確保しましょう。 継続することで、確実に力がつきます。
数学が苦手な方の「やってはいけない」3つの勉強方法
1. 計算練習の軽視
計算練習を怠ると、本番で時間が足りなくなったり、文章題の理解に支障をきたしたりします。
短時間でも継続することが重要です。 1日5分でもいいので、計算問題に触れる習慣をつけましょう。
2. 推論問題を頭の中だけで解く
推論の条件を整理する際、頭の中だけで処理しようとする人がいますが、これは避けるべきです。
頭の中で描いたものは視覚的に確認できないため、書けば気づくはずの事柄を見落とすことが多くなります。 面倒でも実際に書き出すことが、結果的に時間短縮につながります。
3. 「わかったつもり」で学習を終わらせる
間違えた問題の解説を読んだだけで理解した気になり、後日同じ問題でまた間違えるケースがよく見られます。
間違えた問題は、その日の最後にもう一度解いて、確実にできるようになったかを確認しましょう。

\
あなたの現在地を確認しましょう
/
SPI-Hで今どのくらい点数が取れるか、無料の模擬試験で確認してみませんか?
現在の実力を知ることで、効率的な学習計画が立てられます。
【登録不要・無料】
よくある質問
-
SPIの試験種類がわからない場合の判別方法は?
-
ペーパーテスト形式の場合、以下を確認してください:
- 計算問題と文章問題の両方が出題 → SPI-Hの可能性が高い
- 文章問題のみ → SPI-UまたはSPI-Gの可能性
- 計算問題のみ → SPI-Rの可能性
-
合格に必要な点数は?
-
合格点は実施する企業・自治体によって異なります。また、非言語分野だけでなく、言語分野・性格検査も含めた総合的な判断となる場合が一般的です。
お薦めの参考書
SPI-Hの参考書はあまり出ていません。
もっと問題を解きたい方には
「参考書の問題は問題が少ない」「合格を確実にするために、もっと問題を解きたい」
「たくさんの模試に挑戦したい」「適切な出題範囲をしっかりと学習したい」
そのような方は、大人塾のSPIテストセンター対策講座をご検討ください。基礎から無駄なく出題範囲を学習できます。
2011年より5,000名以上の方が受講されています。

学習の進め方に迷ったらカウンセリングを受けましょう(無料)
無料カウンセリングで、あなたの現在の実力と目標に合わせた学習プランをご提案します。
【こんな方におすすめ】
・どの分野から学習すべきか分からない
・自分に合った学習方法を知りたい
・効率的な学習計画を立てたい
💻オンラインカウンセリング
画面から問題を解いていただき、メールで学習の進め方をご提案します。
※オンラインミーティングは実施していません
👥対面カウンセリング(高田馬場)
問題を解いていただいた後、講師が直接アドバイスします。
※遠方でなければ、対面をお勧めします。無理な勧誘はございません